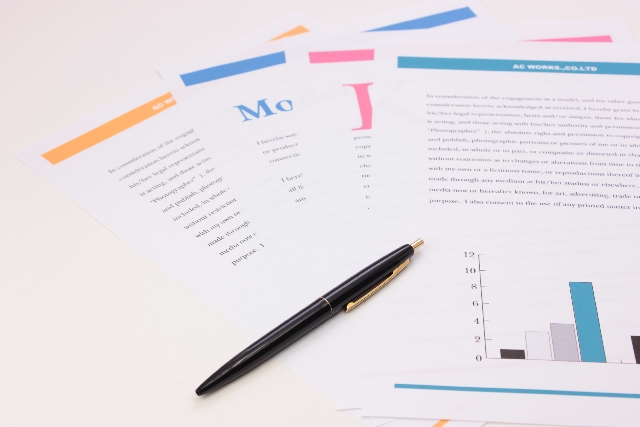


お願いします。良きアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。
出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。
出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
年金は「無職無収入」なら、減免してくれます。離職票と年金手帳をもって退職したら手続きします。
保険は市町村によって違いますが、無職無収入で母子家庭なら減額してくれるかもです。
あと、いやがらせの事実を職安に申し出てください。事情によっては自己都合を会社都合に変更してもらえる可能性もあります。
で、失業保険までのつなぎは、母子寡婦福祉資金で生活費が無利息で借りれる可能性があります。母子福祉課に相談してください。保育所代や学童保育代なども自治体によっては、実情に応じて安くなる可能性もあります。
母子手当ては残念ならが、減額です。が、その翌年は給料があっても手当てが満額もらえます。だから、福祉資金を借りて乗り切ってください。
保険は市町村によって違いますが、無職無収入で母子家庭なら減額してくれるかもです。
あと、いやがらせの事実を職安に申し出てください。事情によっては自己都合を会社都合に変更してもらえる可能性もあります。
で、失業保険までのつなぎは、母子寡婦福祉資金で生活費が無利息で借りれる可能性があります。母子福祉課に相談してください。保育所代や学童保育代なども自治体によっては、実情に応じて安くなる可能性もあります。
母子手当ては残念ならが、減額です。が、その翌年は給料があっても手当てが満額もらえます。だから、福祉資金を借りて乗り切ってください。
雇用保険につて質問です。
パ-トで働いていますが、雇用先との奇妙な契約に疑問があり辞めようかと思案中です。
下記の雇用形態で、失業保険がもらえるのかご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
雇用期間 3月10日~8月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 8月11日~9月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
9月10日~2月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 2月11日~3月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
雇用保険は契約期間は天引きされています。
アルバイト出勤期間は時給も下がる上に出勤も急に告げられるのに出ないと非難されます
(もちろん雇用保険引き落としはありません)
古株の方によると、以前は全員1年契約であったが、雇用保険の加入は無しだったようです。
実質、1年間拘束されているような状態ですが、人員を切るときは半年契約の更新時に「更新しない」と意に沿わない人は
バッサリ切り捨てられているので、明日は我が身かと思い雇用保険のかけ損ではないか不安になりました。
パ-トで働いていますが、雇用先との奇妙な契約に疑問があり辞めようかと思案中です。
下記の雇用形態で、失業保険がもらえるのかご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
雇用期間 3月10日~8月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 8月11日~9月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
9月10日~2月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 2月11日~3月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
雇用保険は契約期間は天引きされています。
アルバイト出勤期間は時給も下がる上に出勤も急に告げられるのに出ないと非難されます
(もちろん雇用保険引き落としはありません)
古株の方によると、以前は全員1年契約であったが、雇用保険の加入は無しだったようです。
実質、1年間拘束されているような状態ですが、人員を切るときは半年契約の更新時に「更新しない」と意に沿わない人は
バッサリ切り捨てられているので、明日は我が身かと思い雇用保険のかけ損ではないか不安になりました。
短期雇用特例被保険者に該当する可能性があります。
1年の算定対象期間中、6ヶ月以上の被保険者期間があればよいとされていますから、特例受給資格者として一時金のかたちで基本手当の日額の40日分が支給されるかもしれません。
質問者さんがどういう待遇なのか、きちんと保険料は納付されているのかを確認しておいたほうがいいと思います。
1年の算定対象期間中、6ヶ月以上の被保険者期間があればよいとされていますから、特例受給資格者として一時金のかたちで基本手当の日額の40日分が支給されるかもしれません。
質問者さんがどういう待遇なのか、きちんと保険料は納付されているのかを確認しておいたほうがいいと思います。
うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
関連する情報